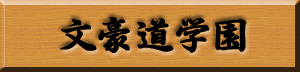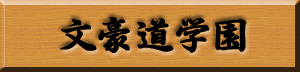|
「あのさ……、やっぱりオレたちちょっと違う気がするんだよね」
深夜の電話でアキラがそう言った時、正直「あー、まただ」と思った。あたしは伸ばした足先でベッド脇のティッシュをたぐりよせながら、努めて冷静に「わかった」と言った。
「最近メールくれないから自然消滅狙ってるんだと思ってた。はっきり言ってくれてよかった。また友達に戻りましょう」
このパターンも三回繰り返すとさすがに慣れる。あたしはティッシュを一枚ひっぱり出すと、受話器を押さえて鼻をかんだ。初めてフラれた時は二十枚必要だった。でも今は一枚で済む。なにごとも場数、だ。
「じゃあこれで」
「うん、今までどうもありがとう」
こうしてあたしの三度目の恋は幕を閉じた。
フラれた理由はわかっていた。あれだ、おにぎりだ。ばあちゃんのおにぎり。あたしの大、大、大好きな味噌おにぎり。
あたしの生まれ育った秋田県のN村では、おにぎりといえば味噌おにぎりのことをさす。
あつあつのごはんをひょいっと握って、味噌樽から自家製の味噌をたっぷりすくって、まんべんなく塗る。ちょうどぼたもちのもち部分をごはんに、あん部分を味噌にした感じだ。学校から帰って、あるいは受験勉強のあとに、忙しい母親に代わってばあちゃんが作ってくれたこのおにぎりは、小さい頃からあたしの一番の元気の素だった。味噌でベタベタになった手をふたりして舐めながら、「うめなうめな」と言っては笑いあったものだ。
だから十八で上京して、東京ではおにぎりといえば海苔で巻いた中に具の入ったものをさすと教えられた時は、誇張ではなしに、天地がひっくり返る思いだった。
あたしが十八年間、おにぎりだと信じていたものは(厳密には)おにぎりではなかったのだ。ああ常識って、思い込みって怖い!
大学に入って、サトルという彼氏ができて、彼が初めてあたしの部屋にやってきた時、あたしはそのことをすっかり忘れていた。小腹が空いたという彼に、あたしは自信満満でおにぎりを握った。ばあちゃんが送ってくれたうちの田舎味噌をたっぷり使って。ところが。
「はいっ!」と満面の笑みで差し出したあたしに彼は言った。「え……、これってなに……」
「え?ああ、これは味噌おにぎりよ。そっか、サトルは東京生まれの東京育ちだもんね。まあ食べてみてよ。すっごく美味しいんだから」
あたしはサトルの手を掴んで、その中におにぎりを握らせた。けれどもサトルは黙って自分の手を見つめるだけでいっこうに口に運ぼうとしない。あたしは構わず自分の手についた味噌を舐めはじめた。ばあちゃんが一年かけて作りあげた大切な味噌だ。粗末にしたらバチがあたる、と教えられてきた。
「ごめんおれ……、遠慮してもいいかな……」
しばしの沈黙のあとサトルは言った。彼はあたしの手におにぎりを戻すと、用事を思い出したと言ってそそくさと帰っていった。そしてそれきり彼から連絡はなかった。
恋人の突然の変貌に納得できず、自宅まで押しかけていったあたしに彼は言った。
「君が味噌だらけの手を犬みたいに舐めてた時、ああほんと人間って外見だけじゃわからないって思ったよ。おれの中で君は山の手のお嬢様って感じだったんだ。アップルパイとか焼いてそうなね。それに味噌って色といい柔らかさといい想像力を刺激するんだよね」
それからだ。あたしが味噌おにぎりを男の試金石として用いるようになったのは。
たとえ両手がベタベタに汚れようと、見た目に多少問題があろうと、そんなことものともしない心の広い男はいないものか!
あたしは携帯からアキラの名前を消し、キッチンに入って缶ビールを呷った。
と、その時。枕の横で再び携帯が鳴った。
「もしもし?」
「あ、よ、よっ、吉川さん?えっとおれ……」
え?キンパチ!?あたしは自分の耳を疑った。三年B組金八先生にそっくりなため、皆からそう呼ばれている男。チビで長髪で年がら年中汗をかいてて。同じゼミなのにまだ一度もまともに喋ったことがない。しかし聞こえてくる声は間違いなくキンパチのものだ。
「あ、あのっ、こ、この前の合宿の時、吉川さんが作ってたおにぎり。じ、実は病みつきになっちゃって……。なんか死んだばあちゃのおにぎりにそっくりなんだよね。それで懐かしくなって自分で作ってみたんだけど同じようにならなくて……。多分味噌が違うと思うんだけど。それでもし差し支えなかったら、味噌のメーカー教えてくれない?」
あたしは驚きで一気に酔いが醒める思いだった。しかも一瞬、ビビッと何かを感じてしまった気が。それにキンパチって実はものすごくいい声?「いいわよ」
そう言った自分の声が、今までになく優しく艶めいていることにあたしは気づいていた。
ああ人間、外見だけじゃわからない。
不思議な喜びが胸に込み上げてくるのを感じながら、あたしは声に出さずにそう呟いた
|